

2025年9月25日 №553
《クラウゼウィッツに学び暑かった8月を送る》
『戦争は政治の延長である』は『戦争論』の核心であるが、別の言葉で言えば『政治を革命せよ、変革せよ』と言っているのである。『戦争論』をよく学ぼう!
ウクライナ戦争や、国連が「ガザは飢饉である」と宣言したイスラエル・ガザ戦争は、クラウゼウィッツの『戦争論』の正しさをよく教えている!
一九四五年の夏(八月十五日)は「日本で一番長い日」であった。戦後80年の今年は、「日本でも世界でも一番長い炎暑」であった。
第二次世界大戦が終わり、今年の八月十五日は、日本が敗北して80年の記念日である。区切りの良い年に、日本では総理大臣が「記念談話」を発表するのが恒例である。
その談話が日本で話題になったのが、社会党の党首であった村山富市首相が発表した「戦後50年談話」である。その特徴は日本が行った戦争は侵略戦争であり、日本は反省し、謝罪する、というものであった。もう一つは二〇一五年、安倍晋三元首相の「戦後70年談話」である。安倍首相は就任するや、早くから村山談話を批判していた。しかしその「安倍談話」には、「村山談話」がそのまま採用され、日本の右翼民族主義者は総反発し、左翼主義への屈服だとして怒りの声が上がったが、それはまさに右翼民族主義の敗北宣言でもあった。
では今年の「戦後80年談話」はどうなったのか。石破総理は当初意欲をもっていたが、保守派の一部から「安倍談話」でもう終わりにしようとの声に押され、別の機会に個人的見解を発表するに変わったのである。石破総理も保守派もみな目先の現象に振り回され、戦争とは何か、がわからない反知性主義に陥っている。小市民的平和主義に堕落していると言っても過言ではない。
確かに、歴史問題については、韓国も中国も静かである。韓国などは日本とは「未来志向で協力しあう」と表明し、「シャトル外交」といわれるものが始まったのである。ここにある本質は何か。いわゆる「歴史問題」は、まさに歴史が解決した、いやいま解決しつつある、と言っていいのである。このことは哲学歴史観の運動法則が生み出した必然の産物であった。歴史科学の運動法則は前へ前へと進む。ここに歴史の偉大さがある。
それにもかかわらず世界を俯瞰すれば、世界は戦争だらけである。われわれ人類、特にマルクス主義者にとっては人類の未来に責任を持たねばならない。
結論は一つである。すべてを哲学的に、すべてを科学的に、すべてを運動する物質の運動法則として認識せよ、と訴える。
ウクライナ戦争は未だ終わりが見えない。トランプ米大統領、ロシアのプーチン大統領ら大国にもてあそばれている。八月十五日(日本時間十六日早朝)、米ロ首脳会談がアラスカ州で開催されたが、あの赤じゅうたんとインパレスの大騒ぎは何事か。戦争にノーベル賞など個人的名誉や経済上の損得を介在させてはならない。『戦争論』の本質をよく知れ、と訴えたい。
『戦争は政治の延長である』とはつまるところ『政治を革命せよ、変革せよ』ということに帰着する。つまり、資本主義が崩壊の時代を迎えている今、歴史はわれわれに新しい時代、コミュニティ共同体への転換、根本的変革を提起しているのである。この観点を土台として『戦争論』の本質をしっかりと学ぼう!
『戦 争 論』(抜粋)
ウィッツ
(一七八〇~一八三一)
レーニンはクラウゼウィッツを高く評価し、次のように言っている。『戦争は別の(すなわち暴力的な)手段による政治の継続にすぎない……。これが戦争史の問題についての偉大な著作家の一人であるクラウゼウィッツの定式であるが、彼の思想は、ヘーゲルによって実り豊かなものに
された。そしてこれこそいつでもマルクスとエンゲルスの見地であって、彼らは、それぞれの戦争を、その時代の当該の関係強国――及びそれらの国の内部のいろいろな階級――の政治の継続とみたのである』(レーニン「第二インタナショナルの崩壊」一九一五年五月)
カルル・フォン・クラウゼウィッツは、ナポレオンがヨーロッパを席捲(せっけん)した時代に活躍したプロシア(後のドイツ帝国)の将軍である。クラウゼウィッツは少年時代からプロシア軍に志願、後にベルリン士官学校の校長となり、参謀総長として、ドイツ軍を再編成した軍人である。クラウゼウィッツは、一八一八年から十二年間にわたって自らの体験を『戦争論』として執筆、彼の死後、夫人と友人の手によって世に出され、各国語にも翻訳された。その後、全世界の軍事専門家にとっては古典的名著となり、各国の士官学校では教材として採用され、ロシア革命の指導者レーニンも高くたたえた。クラウゼウィッツの『戦争論』はまさに実践の総括であり、理論そのものであり、軍事思想である。今も昔もクラウゼウィッツの『戦争論』は右も左も、思想信条を問わず、一流の軍事専門家、偉大な思想家はみな彼を高くたたえている。戦争とは何か、戦争の歴史を考えるものは一度は彼から学ばなければならない。人民戦線の「戦後五十年・アピール」もクラウゼウィッツから学び、クラウゼウィッツの『戦争論』から出発している。
さて、クラウゼウィッツの『戦争論』の核心は何か。その要点は次の点にある。
(一)
戦争は他の手段をもってする政治の継続にほかならない。戦争とは単に政治行動であるのみならず、まったく政治の道具であり、政治的諸関係の継続であり、他の手段をもってする政治の実行である。
政治的意図は目的であって、戦争は手段であり、そしていかなる場合でも手段は目的を離れては考えることはできない。
いかなる事情のもとでも、戦争は独立したものと考えられるべきではなく、一つの政治的道具として考えられるべきである。同時に戦争には、それをひきおこす動機や、事情によってさまざまの種類がある。
政治家および将軍が下すべき第一義的で、もっとも重要な、もっとも決定的な判断は、その着手しようとする戦争について、以上の点を正確に把握することにある。事態の性質上、求めることのできないものを、その戦争において求めたり、おしつけたりしてはならない。これこそすべての戦略問題中の第一義的な、もっとも包括的な問題である。
戦争は真剣な目的にたいする真剣な手段である。戦争は常に政治状態に由来するものであり、政治的動機によってのみよびおこされる。したがって戦争は一つの政治的行為である。
たとえはじめは政治からよびおこされたにしても、戦争はひとたび発生した瞬間から、それは政治にとってかわり、政治から完全に独立したものとして、これを押し退け、ひたすらその独自の法則に従うようになるであろう。それはあたかも、ひとたび導入された地雷が、あらかじめしかけられた方向に向かってのみ爆発するのに似ている。
とはいうものの、政治目的が優先的な考慮の対象とならねばならぬことには変わりはない。かくして政治は全軍事行動に貫徹し、戦争において爆発する力の性質が許すかぎり、これに不断の影響をおよぼすのである。
(二)
戦争を理解するためには、まず第一に政治的要因や事情から生みだされたその性格や輪郭を認識することからはじめねばならない。したがって戦争を指導し、方針を決定すべき最高の立脚点は政治以外のなにものでもありえないことは完全に確実かつ明りょうとなる。
大軍事的事件や、それに関する計画は、純粋に軍事的な判断にゆだねられるべきであると考えることは許せないことであり、有害でさえある。実際の作戦計画の作成にあたって政府のなすべきことについて、純粋に軍事的な判断をさせる目的で軍人に意見を求めるのは事理を誤ったものである。
戦争のために必要な主要計画はすべて政治的事情を理解することなしには作成できるものではない。政治が戦争の遂行に有害な影響をおよぼすということがよくいわれるが
非難されるべきは、政治の影響ではなくて、政治自身なのである。政治が正しければ、つまりそれがその目的に適合しておれば、それは戦争に有利に作用せざるを得ない。
戦争は政治の手段である。それは必然的に政治の特徴を帯びなければならぬ。その規模は政治のそれに対応したものでなければならぬ。したがって戦争の遂行はその根本において政治それ自身である。その場合、政治はペンのかわりに剣を用いるが、それだからといって政治自身の法則にしたがって考えることをやめるわけにはいかないのである。
軍事行動の目標が政治的目的の代用物となると、一般的に軍事的行動は弛緩(しかん)してゆくものであり、戦闘力は衰える。
(三)
戦争というものは、その客観的な性質上、蓋(がい)然性の計算に帰着する。だから偶然性の要素がつきまとう。じっさい、いろいろな人間の活動のうち、戦争ほど不断に、かつ、あらゆる面で、偶然と接触するものはない。
戦争は実に危険な事業であって、このような危険な事業にあっては、お人よしから生まれる誤謬(ごびゅう)ほど恐るべきものはない。
物理的暴力の行使にあたり、そこに理性が参加することは当然であるが、そのさい、一方はまったく無慈悲に、流血にもたじろぐことなく、この暴力を用いるとし、他方にはこのような断固さと勇気に欠けているとすれば、かならず前者が後者を圧倒するであろう。
戦争哲学のなかに博愛主義をもちこもうなどとするのは、まったくばかげたことである。
戦争は暴力行為であり、その行使にはいかなる限界もない。かくして一方の暴力は他方の暴力をよびおこし、そこから生ずる相互作用は、理論上その極限に達するまでやむことはない。
戦争は生きた力が死物に働きかける作用ではない。それは、常に生きた力と生きた力との間の衝突である。というのは、戦う二者の一方が全然受身の地位にあるとすれば、それは戦争とはいえないからである。したがって当事者にとって最悪の状態は、抵抗力の完全なそう失である。
精神的要素は戦争全体を貫いている。物理力と精神力は相互に融合しており、物理力は木で作った槍(やり)の柄であり、精神力は金属で作った槍の穂先である。
クラウゼウィッツの『戦争論』の正しさは広島・長崎の原爆投下という歴史的事実によってその正しさが証明されている。理論を実践的に正しく理解せよ!
日本「降伏」の意向知っていた大統領 狙い
はソ連牽制
二〇一五年六月二日付『朝日新聞』は特集を組んでアメリカの広島・長崎に対する原爆投下は、第二次世界大戦後の新しい国際情勢をにらんだトルーマンアメリカ大統領のソ連に対するけん制であったとする、アメリカン大学の教授で核問題研究所長のピーター・カズニック氏の一文をつぎのように紹介している。
〔日本本土に侵攻すれば、徹底抗戦にあい、米兵らに多くの犠牲が出るだろうとの言説を、当時の米国人らは信じていたのです。年配の世代の人たちは(原爆投下を命じた)トルーマン大統領は英雄だったと信じています。実はトルーマンは日本側が降伏したがっていることを知りながら、かたくなに日本側が求めた降伏文書の文言変更を拒んだりしました。
トルーマンの頭の中にソ連の存在があったのは間違いありません。ソ連が参戦する前に日本の降伏を促したかったのです。原爆投下によって、ソ連に対してメッセージを送ったのです。日本の最高戦争指導会議は1945年5月、ソ連の仲介によって、よりよい降伏文書を得ようとしていました。広田弘毅元首相は駐日ソ連大使に6月初めに会って、一刻も早い降伏の意思を伝えています。
米国が広島・長崎に原爆を投下した時、ソ連の指導者らは真の標的は日本ではなく、自分たちなのだと理解していたはずです。米国の原爆開発を指揮したレスリー・グローブス将軍も『ソ連が我々の敵だ。日本ではない』と明言しています。
トルーマンは『8月15日までにスターリンが対日参戦する。そうしたら日本は敗北する』と述べていました。4月11日や7月2日の機密文書には、『ソ連が参戦したら戦争が終わる。日本はそれ以上抵抗できない』と明記されています。米国は日本側の通信を傍受しており、7月18日の日本側の公電によると、天皇が和平を求めていることをトルーマンとその周辺は知っていたのです。だから、原爆によって戦争を終わらせたのではなくて、戦争が終わる前に原爆を使いたかったのです〕
以上のとおり、アメリカの日本本土に対する原爆投下は、ソビエト政府に対する牽制だったのである。つまり、『戦争論』が指摘する通り、戦争(原爆投下)は政治の道具であった。ここに全てがある。 (以上)
《2面》
われわれは個としては滅するが、類としては英雄記念碑と共に永遠である!
~岡崎旦さんの入魂式開かる~
2025年8月9日、革命英雄記念碑(東京霊園)において、日本共産党(行動派)中央委員会主催の名誉党員・岡崎旦(あきら)さんの記念碑への入魂式が開かれた。平岡恵子書記長の「旦さんは妻である岡崎紀子さんの党活動、機関紙編集活動を長年に亘って立派に支え、日本の革命運動に多大な貢献を果たした」との経過報告がなされ、引き続き、友人を代表して国本真実さん(病気で参列できなかった岡崎紀子さんの代理)の手で森久議長に遺骨が渡され、森議長の手によって記念碑に入魂された。黙祷、森議長挨拶、献花が捧げられ、一部式典は厳粛に執り行われた。
場所を移して二部・懇談会がもたれ、故人の様々な想い出が語られ、一大家族としての強い絆が再確認され、式典は無事終了した。
岡崎旦さんの入魂によせて!
森 久
皆さん、猛暑の中、ご苦労様でした。皆さんの立ち合いのもとで、岡崎旦さんを無事、この英雄記念碑に祭ることができました。有難うございました。炎天下でございますが、すこし時間を頂いて、議長として、ご挨拶を申し上げます。
その眼目を簡単に申し上げれば、岡崎旦さんの英雄記念碑への入魂は必然であった、ということであります。平岡書記長が紹介した略歴の言葉に注目していただきたい。彼の生涯は「研究と現場を結びつける人工林のエキスパート、協力と共同の価値ある人生であった」という一節であります。
彼は林業の科学者であります。林業の成長と発展も科学抜きにはあり得ない。自民党をはじめとする古い政党や社会システムはすでに敗北、終わっています。人類の未来も歴史科学の通りに進んでいます。新しい時代はコミュニティ社会であります。参院選の結果やそれをめぐる混迷はその表れであります。夜明け前が一番暗い、と言われますが、それをいち早く察知するのが、科学者であります。われわれマルクス主義者も社会科学者であります。部門や専門がちがっても科学として一つであります。こういう歴史の流れ、科学的原理が、彼をして記念碑に眠る原動力となったのであります。すべては必然と偶然の産物であります。
夫人の紀子さんが行動派党の党員である、という偶然性もありますが、根本的には、彼とわれわれを結びつけたも
のは現代の歴史時代であり、科学という必然性が支配した結果の産物であります。人類の未来も歴史科学が示す通りであります。マルクス主義への確信を訴えます。
最後に、次の科学的死生観を改めて確認しましょう。
『われわれは個としてはみな滅しますが、類としては記念碑とともに永遠であります』。以上であります。有難うございました。
(二〇二五年八月九日 入魂式によせて 議長挨拶)
「写真」
国本真実さんが遺骨を森久議長に!
「記念碑写真」
54名の英雄を祭る偉大な記念碑!
「写真」
岡 崎 旦
1941年10月4日生
2025年5月23日没
名誉党員
1941年、香川県高松市にて小学校教員であった父岡崎福治、母チヨの4人兄弟の長男として生まる。
鹿児島大学に入学、日本林業の現状と未来について学ぶ。卒業後は「奈良県林業試験場育種技師」として活躍。「花粉症」など現代の諸問題に対する知見や育種技術に果たした貢献は多大であった。
1966年結婚、大学の先輩であった青崎紀子さんと奈良で再会、結婚。妻のご両親は1937年、中国に渡り、民間の航空会社で働き、その3年後に未熟児として生誕、医師に大変世話になったと聞く。ご夫妻、婦人同盟の平岡、3人の友情は兄弟のようでもあった。紀子さんは入党。
1980年7月15日、日本共産党(行動派)再建大会開かる。紀子さんは代議員として出席する。一貫して機関紙編集者として活躍した。
旦さんは非党員であったが、妻の運動については、よき理解者であり、よき支援者であった。経済的激震の時代、自宅の一室を編集室として開放し、妻を大いに助けた。
仕事中の事故で、胸椎切断し車椅子生活となる。長期にわたる療養の末、2025年5月23日、肺炎で死去。彼の生涯は「研究と現場を結びつける人工林のエキスパート、協力と共同の価値ある人生」であった。山の仲間も、7月9日、彼を偲んで散骨した。享年84。
《2面》
第27回参院選自民党惨敗、結党以来、衆・参で初の過半数割れ。これは自民党政治の終焉であり、自民党政治を支えた資本主義経済の終焉と崩壊の狼煙となった!
《2025年7月度政治報告》
日本人民戦線運営委員 梅原秀臣
(広島社会科学研会代表)
はじめに
第27回参議院選挙が7月20日に投開票され、翌日の国内各紙朝刊一面トップ見出しはこぞって「自公 議席大幅削減」、そして22日各紙は改めてトップ見出しで「自公 過半数割れ」と報じた。政権与党自公が昨年の衆院選挙に続いて、参院選でも過半数割れしたのである。自民党が衆参両院で過半数割れし、少数与党の状況に陥ったのは1955年の結党以来、初めてのことであり、まさに異常事態である。
この異常事態は昨日、今日、突然起こったわけではない。そこには歴史があり、科学があり、それは大衆の失望であり、怒りであり、闘いであり、まさにこうしたマグマの爆発であった。それは一言でいえば、度重なる自民党の裏切りに対する国民の怒りの爆発であり、反乱であった。集団的自衛権を認めた戦争法強行採決、裏金問題に代表される政治とカネ、森友・加計問題、公文書改ざんと隠ぺい、統一教会との癒着、さくらを見る会等々(これらの国会答弁はすべて「記憶にない」、「答えられない」のオンパレード)列挙すればきりがないほどの不正、腐敗、裏切り、傲慢と隠ぺい。大衆の我慢も限界に来たというわけである。その意味でもはや自民党の再生はない。
何故か。自民党に代表される保守政党、それは独占資本主義(ブルジョア独裁)の代弁者であり、その土台としての独占資本が今や世界的(アメリカを見よ、ヨーロッパを見よ、わが国の現実を見よ、どこにも安定した政権はなくなった)に崩壊の危機にある。土台(下部構造)がグラついてきたのである。上部構造の自民党(保守政党)とそのイデオロギーがグラつかないわけがない。その危機感から自民党内のみならず、ブルジョア評論家たちも喧々囂々(けんけんごうごう)。「石破は責任をとって退陣せよ」、「いや続投だ」、「一体だれが次の首相をやるのだ」、「借金国を誰が担うのか」、「われわれ(自民党)も一度下野してはどうか」、「下手をしたらイギリスのトラス・ショック(2022年9月、トラス政権の国債依存による大規模減税政策⇒金融市場の大混乱⇒即辞任)の二の舞となるぞ」、「平成の政治改革たる二大政党制も通じない」「大衆迎合・ポピュリズムで政治の劣化だ」等々議論百出。まさにかつてない混迷と混乱である。つまり誰が、あるいはどの党(野党を含め)がやっても、どのような連立を組もうとも、選挙制度(衆愚政治、大衆迎合、ポピュリズム)に基づく議会制民主主義(ブルジョア独裁の衝立)という土俵では同じことであり、崩壊と滅亡である。ここに歴史の運動法則がある。
すべては現代の歴史時代の反映である。アメリカのトランプ政権が再登場し、そのトランプの支持基盤MAGAが早くも分裂の危機にあり(こうしてアメリカはさらなる四分五裂へと分断が進む)、こうして現代資本主義は崩壊し、それに代わる新しい転換の時代を迎えている。日本においてもいよいよその新しい時代が到来したということである。歴史は常に運動し、変化し、発展し、転換していく。
新しい時代とは何か。それは大混乱、大混迷、大激動を通じて、選挙や議会に代わる新しい民主主義、労働者階級と人民のための真の民主主義としての評議会(ソビエト)を生みだし、コミュニティ共同体社会を実現していく時代である。
われわれは単なる評論家であってはならない。以下は歴史が検証したマルクス・レーニン主義に基づく労働者階級と人民のための指針である。歴史はこの指針に基づく人民闘争、人民戦線、人民権力(人民政府)を通じて新しいコミュニティ社会を実現していく。歴史は到達すべきところに必ず到達する。
独占支配とブルジョア独裁は一切の民主主義を否定する。
ある人々は、現代日本のような議会制国家には、制限されているが、一定の民主主義は、不十分ながらも存在している、と主張している。したがってこれらの人物によれば、この不十分な民主主義を利用して闘いながら、これを拡大して、やがて完全な民主主主義にまで高めるべきである、と主張するのである。これは現代修正主義の基本的観点である。
議会制があるから民主主義の一定の条件が存在している、と主張する人々にレーニンはどう答えているのか。彼は有名な著作『国家と革命』(1917年)の中で次のように言っている。
「支配階級のどの成員が、人民を抑圧し、踏みにじるかを数年に一度きめること―議会主義的立憲君主制ばかりでなく、もっとも民主的な共和制の場合にも、ブルジョア議会制度の真の本質はまさにここにある。…アメリカからスイスにいたり、フランスからイギリス、ノルウェーその他にいたる、どの議会主義国でもよいから一瞥してみたまえ。真の『国家』活動は舞台裏で行われ、各省や官房や参謀本部が遂行している。議会では『庶民』を欺こうという特別の目的でおしゃべりをしているに過ぎない。」
すなわちレーニンは、ここで、次のことを明確に教えているのである。すなわち、議会は人民の目をごまかすために、暴力による人民に対する抑圧をごまかすために、そのためのカムフラージュとして、議会を衝立として運用しているのだということ。ある一定の時間、議会でおしゃべりをやらせておきながら、実際は議会の外で、独占ブルジョアジーが着々と既成事実を積み重ねながら、階級支配を実現させているのである、と。
実際、われわれの目の前に展開されている議会もそうである。先に書いた、自民党の裏金問題(政治とカネ)や、森友・加計学園問題、それに絡む公文書の改ざんや隠蔽、統一教会との癒着などの国会答弁を一瞥するだけで、レーニンの主張の正しさが手に取るようによくわかるではないか。さらにレーニンは同論文の中で続けて、資本主義の下における民主主義の本質について次のようにいっている。
「資本主義社会が最も順調に発展するという条件がある場合には、この社会には民主的共和制という形で程度の差はあれ民主主義がある。しかし、この民主主義は、常に資本主義的搾取という狭い枠で狭められているので、実際には、つねに、少数者のための、有産階級だけのための、富者だけのための民主主義にとどまっている。資本主義社会の自由は、つねに、古代ギリシャの諸共和国における自由、すなわち奴隷所有者のための自由と大差のないものにとどまっている。近代の賃金奴隷制は、資本主義的搾取の諸条件のために、今なお窮乏と貧困にひどく押しつぶされているので、彼らには『民主主義どころではなく』また『政治どころではなく』、諸事件が普通の形で平穏にすすんでいる場合には、住民の大多数は公の政治生活への参加から締め出しをくっている。
自由主義的教授や小ブルジョア的日和見主義者が考えているように、この資本主義的民主主義―この不可避的に狭く、貧乏人をこっそり押しのける民主主義、したがって徹頭徹尾、偽善的で、偽りの民主主義―から『ますます完全な民主主義へ』と、単純に、まっすぐに、すらすらと発展が行われるわけではない。そうではない。一層の発展、すなわち共産主義への発展は、プロレタリアートの独裁を通じて行われるのであって、それ以外の進み方はあり得ない。なぜなら、資本家的搾取の反抗を打ち砕くことは、他の誰でもできないし、また他のどんな方法によってもできないからである。しかし、プロレタリアートの独裁、すなわち抑圧するために被抑圧者の前衛を支配階級に組織することは、民主主義の拡大をもたらすだけではない。プロレタリアートの独裁は、民主主義を大幅に拡大し、この民主主義は、はじめて富者のための民主主義ではなしに、貧者のための民主主義、人民のための民主主義になるが、これと同時に、プロレタリアートの独裁は、抑圧者、搾取者、資本家にたいして、一連の自由の除外例をもうける。人類を賃金奴隷から解放するためには、われわれは彼らを抑圧しなければならないし、彼らの反抗を暴力で打ち砕かなければならない。そして抑圧のあるところ、暴力のあるところ、自由がなく、民主主義がないことは明らかである。」
すなわち、資本主義の下では人民のための民主主義はひとかけらもない。存在しているのはブルジョア独裁を維持するための、人々をごまかすための手段としての、偽物の民主主義であり、ブルジョアジーがこれを振りかざしているのだということ。偽物、偽り、ごまかし、そして暴力と抑圧であり、これこそが資本主義的民主主義なのである。この本質を実践的にしっかり掴もうではないか。
ロシア革命の推進力となった評議会(ソビエト)に学ぼう。
1905年に発生したロシアにおける第一革命は、1917年に勝利したロシアにおける社会主義革命の予行演習であった。1月16日、ペテルブルグのプチロフ工場におけるストライキと1月22日の「血の日曜日」から開始され、6月27日の戦艦ポチョムキンの反乱から、12月23日から30日にかけての武装労働者の蜂起と政府軍との市街戦、政府軍による鎮圧、というこの革命戦争の中でソビエトは生まれた。
10月26日、ペテルブルグのプチロフ工場に最初の労働者代表ソビエトが結成され、それはモスクワ、バクーなどロシアの主要都市に拡大された。工場ごとのソビエトは地域ソビエトへ、産業別ソビエトへと進んだ。労働組合、非組合員、政党、政派、宗教に関係なく、そこで働き、そこで生活しているすべての人々の共通の意志によって決議され、承認された、真に大衆を代表する機関としてのソビエトであった。このモデルは軍隊にも波及し、「兵士代表ソビエト」が軍内に、そして農民のあいだには、「農民ソビエト」が生まれた。こうしてレーニンとボリシェビキの指導のもとに、全ロシアに、地域ソビエトから、全国ソビエトへと広がった。これを拠点に、1917年10月の社会主義革命では「全権力をソビエトへ!」という統一スローガンに基づくロシア社会主義革命へと成長転化したのである。
事実が証明した通り、「評議会」とは、人民大衆による「直接民主主義」の形態である。そこで働く、そこで生活する人民大衆が生産点と生活点で、共通の意志と、共同の認識を集団の意志と政策として集約し、これを機関としての「評議会」で確認し、権力の意志として執行していく。これである。
レーニンはロシアにおける第一革命から学んで、10月革命の直前の1917年8月~9月に、先にも紹介した『国家と革命』という論文を発表したが、その中ではっきりと次のように書いている。「20世紀初頭の帝国主義段階におけるプロレタリア革命はパリの労働者が生み出したコミューン制でなければならない。そのロシアにおける具体化がソビエトである」と。
真の民主主義とは、自覚された人民大衆の共同の意志、共通の認識、協同行動に基づく政策の確立と確認、である。人民大衆は、生産点、生活点、つまり労働と生活の中で、互いに協力し、共同し、共通の要求に基づく運動と闘いの中で、連帯し、交流し、自らのコミュニティを作り上げていく。ここに真の民主主義がある。その集大成されたものこそ「評議会」である。
こうした評議会(ソビエト)の決定こそ人民大衆の創意、強固な意志であり、これが大衆の思想となり、この思想と意識のもとでのみ大衆は生死をかけて戦うのである。
評議会に関する理論問題
レーニンは1920年に書いた『独裁の問題の歴史に寄せて』の一文の中で次のように論じている。
「労働者階級と人民の権力、この新しい権力というものは、空から降ってくるものでもなく、地下から湧いてくるものではない。それは旧支配権力と併行して、旧権力に対抗して、旧権力との闘争の中で発生し、成長するものである」と。つまり、評議会という名の人民権力は、大ブルジョアジーの支配権力に対抗する運動と闘い、人民戦線運動の中から必然的に生まれ、成長し、一定の歴史的転換期に爆発し、相転移する。こうして旧権力に取って代わるのである。ここに弁証法的運動法則がある。
さらに、1920年7月に開かれたコミンテルン第2回大会で採択されたその規約はレーニンの提案を採用して次の一節が規定された。
「共産主義インタナショナルは、プロレタリアートの独裁、その形態たるソビエト(評議会)をもって、人類を資本主義の支配から解放する唯一の可能な手段であると考える。そして共産主義インタナショナルは、ソビエト制度を、プロレタリアートの独裁の歴史的形態であることを確認する」と。
マルクスが提起し、レーニンが実現した労働者階級と人民の支配、その権力はまさに「評議会」という直接民主主義であり、間接民主主義と愚民政治の投票による議会主義ではないということを、われわれ正統マルクス主義者と真の革命家は良く認識し、自覚して実践し、行動しなければならない。そのためにもわれわれは「賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)ことを知らねばならない。その歴史とは第一次世界大戦後に発生した、ロシア革命の勝利と、ドイツ革命の敗北であり、第二次世界大戦後に発生した中国革命の勝利と、フランス革命の敗北である。この二つの歴史上の実例の本質と教訓はただ一つ、マルクス主義の理論上の原則に忠実であったかどうか、マルクス主義の思想と理論に従って実践した、行動したのかどうか、ここにすべてがある。勝利したロシア革命と中国革命はマルクス主義の理論に忠実であり、敗北したドイツ革命とフランス革命はマルクス主義の理論上の原則を忘れてしまった。
故にレーニンは明確に断定する。「革命的理論なくして革命運動はあり得ない。…先進的な理論に導かれる党だけが先進的指導者としての役割を果たすことができる」(『何をなすべきか?』レーニン)、「大衆の自然発生的な高揚が高まれば高まるほど、前衛党の理論活動においても、多くの、原則的な、目的意識性が決定的なものとなる」(同上書)。 【後略】
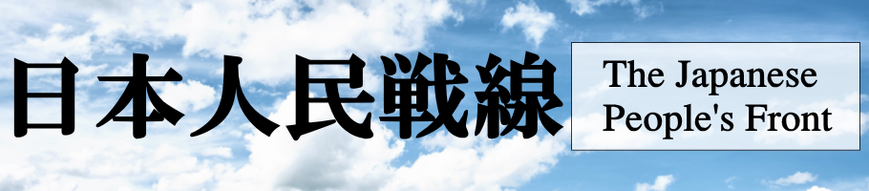
コメントをお書きください